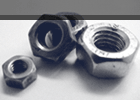ホーム > Mechanical
Desktop > パラメトリックモデリング
| Mechanical Desktopではじめる3次元モデリング |
第11回「パラメトリックモデリング」 |
| 3D CADの特徴として一般に挙げられているもののひとつに、「パラメトリック設計」という概念があります。パラメトリックとは、寸法値を変えることによって図形の形状を変更することができるという意味です。 例えば、MDTでモデリングをするとき、まずは適当な大きさでスケッチを描いて外形線化し、寸法を入力してスケッチの大きさを変えることができます。また、一度寸法拘束をつけてしまっても、寸法編集コマンドで寸法値を変更することができ、形状も変更した寸法に追従して変化します。 MDTではこのパラメトリックの性質を使用したモデリングを行うことができます。 |
||||
| スケッチ間での寸法駆動 |
||||

今回はこのモデルを作成します。 |
||||

|
||||
 円筒部分にあたるスケッチを作成します。 スケッチを外形線化し拘束条件を付加します。 |
||||
 スケッチフィーチャー[回転]コマンドを選択します。 スケッチの底辺を回転軸として選択し、360度回転させます。 |
||||
 円筒部分が完成しました。 |
||||
 次に、円筒部分の底面をスケッチ平面に指定します。 |
||||
 では、寸法拘束を入力します。ここで注目する点は、40、50という寸法はそれぞれ80、100の1/2の値だということです。 モデル完成後、[スケッチ編集]コマンドでこれらのエッジの寸法変更をする場合、全部の寸法を[寸法編集]コマンドで一つ一つ選択し、数値を入力し直すのは手間がかかるかと思います。 そこで、MDTの持つパラメトリック寸法機能を使って、常に1/2の値であるよう設定しましょう。 |
||||
 まずは、寸法の表示形式を変更します。 [パーツ]メニュー[寸法記入]の中に左の寸法表示の形式を選択できる3つのコマンドがあります。 寸法を以下のように表示することができます。 |
||||
 変数とは、各寸法拘束に自動的に割り振られている番号のようなものです。 |
||||
| デフォルトでは数値で寸法が表示されていると思います。 ここで、[数式で寸法表示]を選択しましょう。 |
||||
| 寸法拘束には、数字だけでなく計算式等も入力できます。 まずは[寸法編集]コマンドを選択し、「40」の寸法をクリックします。 |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
 または、寸法を入力する際に[電卓]を使用して数式を適用することもできます。 寸法をとる2点を選択し、寸法値を配置します。その場で右クリックし、メニューから[電卓]を選択します。 |
||||

|
||||
| 電卓ダイアログが表示されます。 | ||||
| |
||||
 左上の数値入力欄にd18が反映されています。 ダイアログ内の電卓キーまたはキーボードのテンキーから「/2」を続けて入力します。 OKを押し、ダイアログを終了します。 |
||||
 電卓ダイアログで設定した数式が、寸法に反映されています。 同じように、寸法100の半分の値である寸法50を数式を設定しながら付加します。 |
||||
 拘束が完成したら、10mm押し出します。 |
||||
 最後に、円筒の先端に3mm面取りをして完成です。 |
||||
| * * * * * * * * | ||||
| 先程数式を入力したスケッチフィーチャーの寸法を変更してみましょう。 Desktopブラウザ上でフィーチャー名を右クリックし[スケッチ編集]を選択します。 80mm→70mm、100mm→90mmにそれぞれ寸法値を変更しましょう |
||||
| |
||||
| |
||||

寸法値の変更が終了したらパーツを更新します。 |
||||
| パラメトリック機能を持つ3D CADの利点として、一度作成した形状の寸法を変更することで容易にパーツの形状変更ができることが挙げられます。 上のパーツでも、例えば寸法を変更することになった時、4つの寸法を入力しなおしてもよいのですが、2箇所に数式を入れておくだけで、随分変更作業が楽になります。 |
||||
| フィーチャー間での寸法駆動 |
||||
 左の2箇所の厚みが常に同じになるよう、寸法拘束を利用して設定しましょう。 |
||||
| (方法1)関連付け | ||||
 Desktopブラウザで、[押し出し距離1]フィーチャーを右クリックし、[編集]を選択します。寸法の表示形式は[数式で寸法表示]にしておきましょう。 Desktopブラウザで、[押し出し距離1]フィーチャーを右クリックし、[編集]を選択します。寸法の表示形式は[数式で寸法表示]にしておきましょう。
|
||||

[距離]数値フィールドで右クリックし、[関連付け]をクリックします。 |
||||
 関連付けられたフィーチャまたは長さ寸法を選択: 関連付けられたフィーチャまたは長さ寸法を選択:とコマンドラインに表示されます。 ここで、モデル上で[回転角度1]フィーチャーの箇所を選択します。 |
||||
 [回転角度1]フィーチャーの寸法が表示されます。ここで同じ値としたい寸法[d8]をクリックします。 [回転角度1]フィーチャーの寸法が表示されます。ここで同じ値としたい寸法[d8]をクリックします。 |
||||
 [押し出し距離1]フィーチャーダイアログが再び表示されます。 [押し出し距離1]フィーチャーダイアログが再び表示されます。[OK]を押してダイアログを閉じ、そしてパーツを更新します。 |
||||
 パーツに変更が反映されました。 |
||||
| (方法2)電卓 | ||||
 上と同じ、押し出しダイアログの、「距離」のスピンコントロールボックス上で右クリックし、メニューから「電卓」を選択します。 |
||||
 電卓ダイアログが表示されます。「アクティブなパーツ変数」タブのd8をダブルクリックし、数値入力欄に値を反映させます。 OKを押して電卓ダイアログを終了します。 |
||||
 「押し出し」ダイアログに戻ります。 「距離」の値にd8が反映されています。 OKを押して押し出しダイアログを終了します。 |
||||
| * * * * * * * | ||||
| では、円筒部分の寸法を変更してみましょう。 | ||||
 回転フィーチャーを右クリックし、「寸法編集」を選択、寸法編集コマンドで値「10」を「20」に変更します。 enterし、パーツを更新します |
||||
 回転フィーチャーの後の押し出しフィーチャーの押し出し距離も追従して大きくなりました。 |
||||
| 以上のようにスケッチ上だけでなく、変数を用いて異なるフィーチャー間でも寸法を拘束することができます。 | ||||
|
|
||||
| 次回は |
||||
|
|
||||
| 今回はパラメトリック機能を利用したパーツの寸法駆動について紹介していきましたが、パーツ作成後に寸法や形状を変更することになった時に便利な機能ですので、ぜひ使ってみて下さい。 |
||||